40代を迎えると、「あれ? 以前より疲れやすい」「体重が落ちにくいな」と感じること、ありませんか?
もし「あるある!」と思ったなら、それは決して気のせいではありません。
実は、私たちの体は確実に変化してきているのです。
では、その変化ってどんなものなのか、一緒に見ていきましょう。
まず注目したいのが基礎代謝です。
基礎代謝とは――じっとしていても呼吸や心臓の鼓動、体温維持などで消費されるエネルギー量のこと。
20代をピークに少しずつ下がり、40代になるとなんと20代の頃より1日あたり約200〜400kcalも低くなると言われます。
これ、ご飯お茶碗1杯分以上の差なんですよ。
同じ食事量でも、じわじわ体重が増えてしまう理由、少し見えてきましたね。
さらに、ホルモンバランスの変化、筋肉量の減少、睡眠の質の低下、ストレス耐性の弱まり――。
こうした要素が重なって、疲れやすさや体型の変化、集中力の低下といった「40代ならではの不調」が現れやすくなるわけです。
でも、ここで落ち込む必要はありません。
むしろ今こそチャンスです。
体と生活習慣の変化を理解し、ちょっとした工夫を積み重ねれば、40代からでも健康と活力をしっかり取り戻せます。
そして、この年代からの習慣づくりは、50代・60代以降の生活の質をぐんと引き上げてくれます。
これからこの記事で、私が健康管理の専門家として知っていること、そして多くの40〜50代の方をサポートしてきた経験から得たことを、「今日からできる健康&生活習慣のノウハウ」としてお話ししていきます。
 meibu
meibuさあ、一緒に学びながら、未来の自分を元気にしていきましょう!
第1章:40代からの体と心の変化を知る
40代は、「変化の入り口」に立つ年代です。20代・30代では意識しなくても維持できていた体力や集中力が、少しずつ変化してきます。これを単なる“老化”と捉えるのではなく、「体の仕様が変わってきた」と理解することが第一歩です。
ここでは、代表的な4つの変化と、その背景について解説します。
1. 基礎代謝の低下
基礎代謝とは、何もしていない状態でも生命維持のために使われるエネルギーのこと。呼吸・体温維持・心臓の鼓動などに必要なエネルギーです。
- 20代女性の基礎代謝:平均1,200〜1,300kcal
- 40代女性の基礎代謝:平均1,000〜1,150kcal
わずかな差のように見えますが、毎日200kcal減ると、1年で約73,000kcalの差になります。これは脂肪に換算すると約10kg分。
「食べる量は変わらないのに太った」というのは、この差が大きな要因です。
基礎代謝は筋肉量と比例します。筋肉が減ると代謝も落ちるため、軽い筋トレや日常の運動が重要です。
2. ホルモンバランスの変化
40代に入ると、性ホルモン(女性はエストロゲン、男性はテストステロン)の分泌が少しずつ減少します。
- 女性の場合:更年期の前兆として、月経周期の変動や気分の波が出やすくなります。
- 男性の場合:「男性更年期」と呼ばれる疲労感・気力低下が出ることがあります。
ホルモン変化は自然な現象ですが、生活習慣や食事によって症状の程度を緩和できます。
3. 睡眠の質の低下
「寝ても疲れが取れない」「夜中に目が覚める」という声は40代で増えます。
これは、深い睡眠(ノンレム睡眠)の時間が年齢とともに減るためです。
- 睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が減る
- ストレスや不安感で交感神経が優位になりやすい
結果として、睡眠の“量”は足りていても“質”が下がります。
4. ストレス耐性の変化
40代は、家庭・仕事・介護など複数の役割を担うことが多く、精神的負荷が高まります。
さらに、加齢による神経系の変化で、ストレスに対する回復力(レジリエンス)が低下しやすくなります。



無理にストレスをゼロにするのではなく、上手に「逃がす」習慣を持つことが大切です。
40代は、代謝・ホルモン・睡眠・ストレスといった体と心の“土台”が少しずつ変化する時期です。
この変化を正しく知ることで、「何となく不調」を放置せず、早めに対策が打てます。
第2章:日常でできる運動習慣
「運動は健康に良い」とわかっていても、40代になると仕事や家庭の用事に追われ、まとまった運動時間を確保するのは難しいものです。
そこで重要なのが、“短時間でも続けられる運動習慣”を作ることです。
1. 筋肉量を維持するための軽い筋トレ
基礎代謝を下げないためには、筋肉を維持することが不可欠です。特に下半身の筋肉は全身の筋肉の約70%を占めるため、ここを鍛えると効率よく代謝アップが狙えます。
おすすめメニュー(1日10分)
- スクワット(10回×2セット)
脚・お尻・体幹を同時に鍛えられる基本動作。 - プランク(30秒×2セット)
腹筋だけでなく背中・肩も鍛えられる体幹トレーニング。 - カーフレイズ(つま先立ち)(15回×2セット)
ふくらはぎを鍛え、血流改善や冷え対策に効果的。
✓ 正しいフォームを優先し、回数より質を意識する
✓ 朝や夕方の 隙間時間 に行う
2. 有酸素運動で心肺機能をキープ
筋トレに加え、ウォーキングや軽いジョギングを取り入れることで、心肺機能の低下を防ぎます。
ウォーキングのコツ
- 週3〜5回、20〜30分を目安
- 姿勢を正し、腕を自然に振る
- 会話ができるくらいの“やや早歩き”が理想
「時間が取れない」という方は、
- 通勤時に一駅分歩く
- エスカレーターではなく階段を使う
といった日常動作を活用しましょう。
3. 無理なく続けるための習慣化の心理テク
新しい習慣は「やるぞ!」という意志だけでは続きません。
心理学では、**“きっかけ(トリガー)とセットで行動する”**と定着しやすいとされています。
例:
- 朝の歯磨き後にスクワット
- 夕食後のテレビ前でストレッチ
- コーヒーを飲む前にプランク30秒
これにより「特別な運動時間を作る」必要がなくなり、継続率が大きく上がります。
💡 ここまでのまとめ
習慣化は日常動作とセットにする
筋トレは下半身を中心に
有酸素運動は会話できるペースで
第3章:40代の食生活改善ポイント
40代の食事で大切なのは、「量より質」 です。
基礎代謝が落ちているため、若い頃と同じ食事量ではエネルギー過多になりやすく、体重や血糖値のコントロールが難しくなります。
しかし、ただ食事量を減らすだけでは、筋肉や骨、ホルモンの材料となる栄養まで不足してしまいます。
ここでは、健康と活力を保つための3つのポイントをご紹介します。
1. 「腹八分目」とタンパク質重視の食事
腹八分目は、食べ過ぎを防ぐだけでなく、消化器官の負担軽減や血糖値の安定にもつながります。
特に意識したいのがタンパク質。筋肉・皮膚・髪・ホルモンなど、体のあらゆる組織の材料になります。
- 目安:体重1kgあたり1.0〜1.2g/日
(例:体重60kgなら60〜72g) - おすすめ食材:鶏むね肉、魚、大豆製品、卵、ヨーグルト



1回の食事で20g前後のタンパク質を摂るように分けると吸収効率が良くなります。
2. 野菜・発酵食品で腸内環境を整える
腸内環境は免疫力やメンタルにも影響します。
- 食物繊維(野菜・海藻・きのこ):腸内の善玉菌のエサになる
- 発酵食品(納豆・味噌・ヨーグルト・キムチ):善玉菌そのものを補う
ポイントは毎日少しずつ摂ること。
腸内細菌は1〜2日で変化するため、継続がカギです。
3. 糖質・脂質との上手な付き合い方
糖質は大切なエネルギー源ですが、摂りすぎは血糖値の急上昇を招き、肥満や生活習慣病のリスクを高めます。
- 主食は白米よりも雑穀米・玄米を
- 甘い飲み物はできるだけ控える
- 食事の最初に野菜やタンパク質を摂る(食後の血糖値上昇を緩やかにする効果)
脂質は質の良い油を選びましょう。
- 良い油:オリーブオイル、えごま油、青魚の脂(EPA・DHA)
- 控えたい油:トランス脂肪酸(マーガリン、ショートニングなど)
4. 水分補給の重要性
年齢とともに喉の渇きを感じにくくなりますが、脱水は代謝や血流を悪化させます。
- 目安:1.5〜2L/日
- 水やお茶を中心に、常温がベター
腹八分目+タンパク質で代謝を支える
水分はこまめに補給
野菜&発酵食品で腸を元気に
第4章:睡眠の質を上げる生活習慣
40代になると、「寝ても疲れが取れない」「夜中に目が覚める」といった悩みが増えます。これは、加齢による深い睡眠(ノンレム睡眠)の減少や睡眠ホルモン・メラトニンの分泌低下が背景にあります。
しかし、日常生活の工夫で睡眠の質は十分に改善できます。
1. 寝る前90分の過ごし方
睡眠のカギを握るのは、**「寝る直前」ではなく「寝る前90分」**です。
この時間帯に体温をゆるやかに下げ、脳をリラックスさせると入眠がスムーズになります。
おすすめルーティン
- 軽いストレッチやヨガで筋肉をほぐす
- ぬるめのお風呂(38〜40℃)に15分ほど浸かる
- スマホ・PCは極力見ない(ブルーライトが脳を覚醒させるため)



お風呂は寝る90分前に入ると、ちょうど入眠時に深部体温が下がりやすくなります。
2. ブルーライトと睡眠の関係
スマホやPCから発せられるブルーライトは、目に入ると脳が「今は昼だ」と勘違いし、メラトニンの分泌を抑えてしまいます。
- 寝る1時間前からはスマホ・PCをオフ
- 難しい場合はブルーライトカットメガネや画面設定を活用
3. 寝室環境の工夫
寝室は「眠るためだけの空間」に近づけるほど、睡眠の質は高まります。
- 温度:夏は26〜28℃、冬は18〜20℃が目安
- 照明:暖色系の間接照明でリラックス効果
- 音:静かな環境が理想だが、気になる場合は小さな環境音(雨音や波音など)を流す
4. カフェイン・アルコールの影響
- カフェインは摂取後4〜6時間、脳を覚醒させます。午後3時以降は控えるのがおすすめ。
- アルコールは寝つきを良くするように感じますが、深い睡眠を減らし夜中の覚醒を増やします。習慣化は避けたいところです。
💡 ここまでのまとめ
- 寝る前90分はリラックスモードへ
- ブルーライトは最小限に
- 寝室は快適な温度・照明・音環境に
- カフェイン・アルコールの摂取時間に注意
寝る前90分はリラックスモードへ
ブルーライトは最小限に
寝室は快適な温度・照明・音環境に
カフェイン・アルコールの摂取時間に注意
第5章:ストレス管理とメンタルケア
40代は、人生の中でもっとも「役割」が多くなる時期です。
仕事では中堅から管理職へと責任が増し、家庭では子育てや親の介護が重なることもあります。
その結果、心の疲れを感じやすくなり、放置すると睡眠障害・免疫低下・生活習慣病のリスク増加につながります。
ここでは、日常に取り入れやすいストレス対策を紹介します。
1. マインドフルネス・瞑想の活用
マインドフルネスとは、「今この瞬間」に意識を向けることで、過去や未来への不安から解放される方法です。
近年、脳科学の分野でもストレス軽減・集中力向上・感情コントロールに効果があることが確認されています。
1日5分の呼吸瞑想(例)
- 椅子に腰掛け、背筋を軽く伸ばす
- ゆっくり鼻から息を吸い、口から吐く
- 呼吸の感覚に意識を集中
- 雑念が浮かんだら「考えているな」と気づき、また呼吸へ戻す



完璧に無心になる必要はなく、「気づいたら戻す」を繰り返すだけでOK。
2. 趣味やコミュニティとのつながり
人間関係は、ストレスの防波堤になります。
特に40代は、仕事や家庭以外の「第三の居場所」があると心の安定につながります。
例:
- 同好会や習い事(音楽・スポーツ・園芸など)
- オンラインコミュニティ(読書会・趣味のSNSグループ)
- ボランティア活動
3. 感情の整理法(ジャーナリング)
ジャーナリングとは、頭に浮かんだことを紙に書き出し、感情を整理する方法です。
心理学では、書くことで思考が客観化され、ストレスが軽減するとされています。
やり方
- ノートや紙を用意
- 思ったことを5分間、文章でも箇条書きでも自由に書く
- 書き終えたら読み返し、必要なら解決策を一つだけ考える
4. 運動によるメンタル改善
軽い有酸素運動は、脳内のセロトニンやエンドルフィンの分泌を促し、自然な抗うつ作用があります。
特にウォーキングやサイクリングはストレス低減効果が高く、実践しやすい方法です。
💡 ここまでのまとめ
運動は心にも効く薬
マインドフルネスで「今」に集中
趣味・コミュニティで孤立感を減らす
ジャーナリングで感情を整理
第6章:40代が避けたいNG習慣
40代は、体力・代謝・回復力が少しずつ落ち始める年代です。
この時期に知らず知らずのうちに続けている習慣が、将来の健康リスクを高める原因になることがあります。
ここでは特に避けたい習慣と、その理由を紹介します。
1. 睡眠不足を慢性化させる
「忙しいから」と睡眠時間を削るのは、心身のダメージを積み重ねる行為です。
- 睡眠不足は免疫力低下・肥満・高血圧・糖尿病リスク増加と直結
- 脳の記憶力・判断力も低下し、仕事や生活の質が下がる
改善策
- 1日7時間前後の睡眠を確保
- 睡眠時間が取れない日は昼休みに10〜20分の昼寝を取り入れる
2. 暴飲暴食や不規則な食生活
40代は代謝が低下しているため、過食や深夜の食事が脂肪として蓄積されやすくなります。
特に夜遅い食事は、睡眠の質も下げてしまいます。
改善策
- 夕食は就寝2〜3時間前までに
- 外食や飲み会では、最初にサラダやタンパク質を摂る
3. 長時間の座りっぱなし
「座りすぎ」は、喫煙に匹敵する健康リスクと言われています。
- 血流が悪くなり、血栓や心疾患のリスク増加
- 腰痛・肩こり・むくみの原因にも
改善策
- 1時間に1回は立ち上がってストレッチ
- 立ってできる作業(電話・資料読み)を取り入れる
4. 無理な若返り法への依存
極端な食事制限や過度なサプリ・美容医療は、一時的な変化があっても健康を損なうリスクがあります。
- 栄養不足やホルモンバランスの乱れを引き起こす可能性
- 精神的にもプレッシャーや自己否定感を助長
改善策
- 「今の自分を健康に保つ」ことを第一に
- 医師や管理栄養士など専門家の意見を参考にする
💡 ここまでのまとめ
健康より見た目を優先する極端な方法は危険
睡眠不足は“慢性疲労”の入り口
暴飲暴食は代謝低下期の大敵
座りすぎは生活習慣病リスクを高める
第7章:まとめと行動プラン
40代は、体と心の「仕様」が大きく変わる時期です。
基礎代謝の低下、ホルモンバランスの変化、睡眠の質の低下、ストレス耐性の低下など――これらは避けられない自然な流れですが、正しい知識と日々の工夫で、その影響を最小限に抑えることができます。
1. 記事全体の振り返り
- 体と心の変化を知る → 代謝や睡眠の変化を理解し、対策を立てる
- 運動習慣 → 筋トレ+有酸素運動を日常動作と組み合わせて継続
- 食生活の改善 → 腹八分目+タンパク質、腸内環境を整える食事
- 睡眠の質向上 → 寝る前90分のルーティン、環境の最適化
- ストレス管理 → マインドフルネス、趣味、感情の整理
- 避けたいNG習慣 → 睡眠不足・暴飲暴食・座りすぎ・極端な若返り法
2. 明日から始められる3つの習慣チェックリスト
✅ 毎日10分の運動
(スクワット・プランク・ウォーキングなど)
✅ 食事は腹八分目+タンパク質意識
(鶏むね肉、魚、大豆製品、卵などをバランスよく)
✅ 寝る前90分はリラックスタイム
(スマホを置き、軽いストレッチや読書)
3. 小さく始めることの重要性
大きな目標は立派ですが、最初から完璧を目指すと続きません。
まずは「これならできそう」という1つの習慣から始めることが成功の秘訣です。
健康管理は短距離走ではなくマラソンです。
40代からの数年間の積み重ねが、50代・60代の体力や生活の質を決定づけます。
💬 最後に
今日が、あなたのこれからの健康を変えるスタートの日です。
完璧でなくても、昨日より一歩でも健康に近づく行動を選び続ければ、体も心も必ず応えてくれます。
「未来の自分のために、今日の一歩」を大切にしていきましょう。

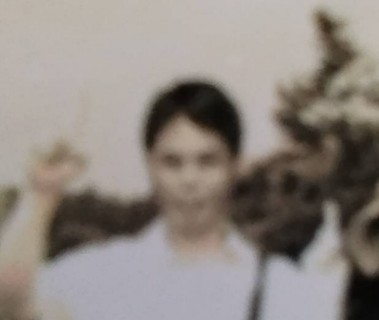








コメント