20代の頃は「46歳なんてまだまだ先の話」って思っていませんでしたか? でも気がつけば、あの頃思い描いていた「大人」の年齢になっている自分がここにいます。
そして同時に、これまで以上に学び続けることの重要性を実感している今日この頃です。
コーヒーを飲みながら、これからの人生について考えてみました。人生100年時代と言われる現代、46歳はまだまだ折り返し地点。残りの人生をより豊かに、より意味のあるものにするために、今から学んでおくべきことは?っ
そう考えた時、3つの大切なことが浮かび上がってきました。今日は、同世代の皆さんと、そしてこれから46歳を迎える皆さんと、その思いを共有したいと思います。
デジタルリテラシー ~新しい言語を学ぶように~

なぜ今、デジタルなのか
「もう46歳だから、スマホは電話とメールができれば十分」そう思っている方もいるかもしれません。でも、それは江戸時代の人が「馬で移動できるから、電車なんて必要ない」と言っているのと同じかもしれません。
今、私たちの周りでは急速にデジタル化が進んでいます。銀行の窓口に行くと「ネットバンキングをお使いください」と案内され、役所では「マイナンバーカードで手続きを」と言われ、お店では「QRコード決済はいかがですか」と聞かれる。これらは単なる「便利なサービス」から「必要不可欠なスキル」へと変わりつつあります。
具体的に何を学ぶべきか
デジタルリテラシーと聞くと「プログラミングを学ばなきゃ」と思う人がいますが、それは料理を始めるのに「まずはフランス料理から」と言っているようなもの。まずは基本的なことから始めましょう。
スマートフォンとタブレットの活用
まるで新しい楽器を覚えるように、最初はぎこちなくても、毎日少しずつ触れていくことで自然に操作できるようになります。私がおすすめするのは「一日一つ新しい機能を試す」こと。今日はカメラで写真を撮って家族に送る、明日は天気アプリで一週間の予報を確認する、といった具合です。
クラウドサービスの理解と活用
「クラウド」という言葉を聞くと、空に浮かぶ雲を想像してしまいますが、実際には「インターネット上の倉庫」だと考えるとわかりやすいです。GoogleドライブやiCloudは、自分専用の倉庫をインターネット上に持っているようなもの。写真や文書を預けておけば、どこからでもアクセスできます。
例えば、旅行の写真をクラウドに保存しておけば、スマホが壊れても写真は安全です。まるで大切なものを銀行の貸金庫に預けるように、デジタルの貴重品も安全な場所に保管できるのです。
AI(人工知能)との付き合い方
AIと聞くと、映画の中のロボットを想像する人もいるでしょう。でも実際のAIは、もっと身近で実用的な存在です。Google検索の予測変換、Amazonの商品おすすめ、スマホの音声アシスタント。これらはすべてAIの技術です。
最近話題のChatGPTのようなAIチャットボットは、まるで物知りな図書館の司書さんのような存在。わからないことがあったら気軽に質問できる、そんな感覚で使ってみてください。「今日の夕食、何を作ろうかな」と相談すれば、冷蔵庫にある材料を元にレシピを提案してくれます。
学習のコツ
デジタル技術を学ぶ上で大切なのは「完璧を目指さない」こと。車の運転を覚えた時のことを思い出してください。最初はウィンカーを出すタイミングに戸惑い、駐車も何度も切り返していたはずです。でも今では無意識にできている。デジタル技術も同じです。
また、「失敗を恐れない」ことも重要です。スマホやパソコンは、間違った操作をしても爆発するわけではありません。「あ、間違えた」と思ったら、一つ前の画面に戻ればいいだけ。まるでテレビのチャンネルを間違えた時のように、別のボタンを押せば解決します。
私は「デジタルデトックス」という言葉には少し違和感を感じています。確かにスマホに依存しすぎるのは良くありませんが、デジタル技術そのものを避けるのではなく、「上手に付き合う方法」を学ぶことが大切だと思うのです。
健康リテラシー:自分の体と向き合う知恵
46歳の体からのメッセージ
20代の頃は、多少無理をしても翌日にはケロッとしていました。徹夜でゲームをしても、朝からバリバリ働けた。でも46歳の今、体は正直です。「昨日少し食べ過ぎたな」「最近運動してないな」「ストレス溜まってるな」そんなメッセージを、体のあちこちから受け取るようになりました。
これは決してネガティブなことではありません。車のメンテナンスランプが点灯するように、体も「そろそろお手入れの時期ですよ」と教えてくれているのです。このメッセージを無視せず、きちんと向き合うことが、これからの健康な人生の基盤となります。
予防医学の考え方を身につける
「予防は治療に勝る」という言葉があります。これは、病気になってから治すよりも、病気にならないよう予防する方が良い、という意味です。まるで家のメンテナンスと同じですね。雨漏りしてから屋根を直すより、定期的に点検して補修する方が、結果的に費用も時間も節約できます。
定期検診の重要性を理解する
「体調が悪くないから病院に行く必要はない」そう考える人は多いです。でも、これは車検を「エンジンがかかるから必要ない」と言っているのと同じ。見た目には問題なくても、内部では小さな異常が始まっているかもしれません。
私は40歳を過ぎてから、人間ドックを受けるようになりました。最初は「面倒だな」と思っていましたが、今では「年に一度の体の通信簿」として楽しみにしています。数値が改善していると嬉しいし、悪化していれば生活習慣を見直すきっかけになります。
生活習慣病との向き合い方
糖尿病、高血圧、脂質異常症。これらの生活習慣病は「サイレント・キラー」と呼ばれます。音を立てずに忍び寄る忍者のように、自覚症状がないまま進行し、気づいた時には重大な合併症を引き起こしていることがあります。
でも、これらの病気は「生活習慣病」という名前の通り、生活習慣を変えることで予防や改善が可能です。急に生活をガラッと変える必要はありません。エレベーターの代わりに階段を使う、一駅手前で降りて歩く、夜食を控える。小さな変化の積み重ねが、大きな効果を生みます。
運動習慣:投資としての運動
「運動しなきゃ」と思うと、なんだか義務のように感じてしまいます。でも、運動を「将来への投資」と考えてみてください。銀行に貯金するように、筋肉や心肺機能に「健康」を貯金するのです。
筋力の維持と向上
筋肉は「use it or lose it(使わなければ失う)」という性質があります。使わない筋肉は、まるで使わない道具が錆びるように、どんどん衰えていきます。特に下半身の筋力低下は、将来の歩行能力に直結します。
私がおすすめするのは「ながら運動」です。テレビを見ながらスクワット、歯磨きをしながらかかと上げ、電話をしながら足踏み。特別な時間を作らなくても、日常の中に運動を組み込むことができます。
有酸素運動の効果
有酸素運動は、まるで体のお掃除のような効果があります。血液の流れが良くなり、老廃物が排出され、新鮮な酸素が体の隅々まで運ばれます。ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリング。どれも特別な技術は必要ありません。
私は週に3回、30分のウォーキングを続けています。最初は「30分も歩くなんて」と思っていましたが、お気に入りの音楽やポッドキャストを聞きながら歩くと、あっという間です。今では、歩いた日と歩かなかった日の体調の違いがはっきりとわかるようになりました。
睡眠の質を上げる
睡眠は、体と心の「リセットボタン」です。パソコンも長時間使っていると動作が重くなり、再起動すると元通りになります。人間の体も同じで、質の良い睡眠によって日中の疲れがリセットされ、翌日に備えることができます。
睡眠の量より質
「8時間寝なければ」と時間にこだわる人がいますが、大切なのは時間より質です。短くても深い睡眠の方が、長くても浅い睡眠より疲労回復効果があります。
睡眠の質を上げるために、私が実践していることをご紹介します。寝る2時間前からはスマホやテレビを見ない(ブルーライトが睡眠を妨げるため)、寝室の温度を少し低めに設定する(18-22度が理想)、お気に入りのアロマオイルを使う(ラベンダーの香りはリラックス効果があります)。
コミュニケーション能力:人とのつながりを深める技術
なぜ46歳でコミュニケーションなのか
「今さらコミュニケーションを学ぶって、おかしくない?」そう思う人もいるでしょう。確かに、46年間生きてきて、人との会話ができないわけではありません。でも、これまでのコミュニケーションを振り返ってみてください。本当に相手の心に響く会話ができていたでしょうか。
人生の後半戦に入る今、これまで以上に人とのつながりが重要になってきます。仕事でも、家庭でも、地域社会でも、より深く、より意味のある関係を築いていく必要があります。そのためには、これまでとは違ったレベルのコミュニケーション能力が求められるのです。
聞く技術を磨く
「話し上手は聞き上手」という言葉があります。面白い話ができる人よりも、話を聞いてくれる人の方が好かれる、という意味です。これは、人間の根本的な欲求「理解されたい」「認められたい」に関わっています。
アクティブリスニングの実践
ただ黙って聞くのではなく、「積極的に聞く」技術があります。まるで優秀な記者のように、相手の話に興味を持ち、質問を投げかけ、感情に寄り添います。
例えば、友人が「最近仕事が大変で…」と話し始めたとします。「大変ですね」と言うだけでは、表面的な反応です。「どんなところが特に大変なんですか?」「それは確かにストレスですね。どうやって乗り切っているんですか?」このように、相手の話をより深く理解しようとする姿勢が大切です。
共感と同情の違い
共感と同情は似ているようで、まったく違います。同情は「かわいそうに」と上から目線で見ることですが、共感は「その気持ち、わかります」と同じ目線に立つことです。
共感を示すには、自分の似たような経験を思い出し、その時の感情を蘇らせることが効果的です。「私も転職の時、同じような不安を感じました」「子育てで悩んだ時期、本当に辛かったです」このように、自分の体験と重ね合わせることで、より深い共感を表現できます。
伝える技術を向上させる
聞く技術と同じように、伝える技術も磨く必要があります。年齢を重ねると、どうしても「昔話」が多くなりがちです。「俺の若い頃は…」「昔はそんなことなかった」このような話し方は、相手を遠ざけてしまいます。
ストーリーテリングの活用
単なる情報の羅列ではなく、ストーリー(物語)として伝えると、相手の記憶に残りやすくなります。ビジネスのプレゼンでも、家族との会話でも、この技術は有効です。
例えば、「節約の大切さ」を伝えたいとします。「お金は大切だから節約しなさい」と言うより、「昔、祖母が戦時中の話をしてくれたんだけど、一粒のお米も無駄にしなかった。その習慣が、戦後の復興の力になったんだって」というように、エピソードを交えると説得力が増します。
相手に合わせたコミュニケーション
同じ内容でも、相手によって伝え方を変える必要があります。まるで言語を使い分けるように、相手の年齢、立場、関心事に合わせてコミュニケーションスタイルを調整します。
若い部下に対しては、彼らが理解しやすい例え話やデジタル用語を使う。年配の方には、ゆっくりとした口調で、丁寧な言葉遣いを心がける。子どもには、彼らの目線に合わせた簡単な言葉で説明する。このような配慮が、円滑なコミュニケーションにつながります。
デジタル時代のコミュニケーション
現代のコミュニケーションは、対面だけではありません。メール、LINE、Zoom会議。これらのデジタルコミュニケーションにも、それぞれのマナーやコツがあります。
メールとメッセージアプリの使い分け
メールは正式な文書、LINEは気軽な会話。この使い分けを理解することが大切です。会社の重要な報告をLINEで送ったり、友人との軽い約束をフォーマルなメールで送ったりすると、相手は違和感を覚えるでしょう。
また、文字だけのコミュニケーションでは、感情が伝わりにくいという問題があります。「ありがとう」と「ありがとう😊」では、相手が受ける印象がまったく違います。絵文字や顔文字を適度に使うことで、文字に温度を加えることができます。
オンライン会議での振る舞い
Zoom会議やTeamsミーティングでは、対面とは異なるマナーが必要です。マイクのオン・オフのタイミング、カメラの角度、背景の配慮。これらは新しい時代のビジネスマナーとして身につけておくべきスキルです。
私が気をつけているのは「画面の向こうにも人がいる」ということを忘れないことです。画面を見ていると、まるでテレビを見ているような感覚になってしまいがちですが、実際には生身の人間とコミュニケーションを取っているのです。
世代を超えたコミュニケーション
46歳の私たちは、上は70代の親世代、下は20代の若い世代と接する機会が多い年代です。世代間のコミュニケーションには、それぞれの特徴を理解することが重要です。
年上の方とのコミュニケーション
経験豊富な年上の方からは、学ぶべきことがたくさんあります。ただし、「教えてもらう」姿勢だけでは、対等な関係は築けません。相手の経験を尊重しながらも、現代の視点や情報を提供することで、双方向の豊かな会話が生まれます。
年下の方とのコミュニケーション
若い世代に対して「最近の若い人は…」と決めつけるのは禁物です。彼らは私たちとは異なる環境で育ち、異なる価値観を持っています。その違いを「間違い」ではなく「多様性」として受け入れ、互いに学び合う関係を築くことが大切です。
これからの学びへの心構え
学び続けることの意味
「46歳になってから新しいことを学ぶなんて遅いんじゃないか」そう思う人もいるでしょう。でも、学びに遅すぎるということはありません。むしろ、人生経験を積んだ今だからこそ、学んだことを深く理解し、実践に活かすことができるのです。
例えば、20代の頃に学んだことは「知識」として頭に入っていても、実際の経験と結びついていませんでした。でも今なら、学んだことをすぐに実生活で試し、その効果を実感できます。料理のレシピを覚えるように、学んだことを実際に「味わう」ことができるます。
完璧を求めすぎない
新しいことを学ぶとき、どうしても完璧を求めがちです。でも、完璧を目指すあまり、学ぶこと自体を諦めてしまっては本末転倒です。
私がプログラミングを学び始めた時のことです。最初は「エラーが出ると落ち込む」「思うように動かないとイライラする」そんな状態でした。でも、ある日気づいたんです。エラーは「失敗」ではなく「学習の機会」だということに。エラーが出るたびに、一つずつ問題を解決していく。その積み重ねが、確実なスキルアップにつながります。
継続の力を信じる
「継続は力なり」古い言葉ですが、これほど真実な言葉はありません。一日10分でも、毎日続けることで、1年後には大きな変化が生まれます。
水滴が石を穿つように、小さな学びの積み重ねが、やがて大きな成果となって現れます。今日から始める小さな一歩が、5年後、10年後の自分を大きく変えるのです。
まとめ:46歳からの新しいスタート
46歳という年齢は、決してゴールではありません。むしろ、これまでの経験という土台の上に、新しい知識とスキルを積み上げる絶好の機会です。
デジタルリテラシーは、これからの社会で必要不可欠な新しい言語です。健康リテラシーは、人生100年時代を健やかに過ごすための投資です。そして、コミュニケーション能力は、豊かな人間関係を築き、意味のある人生を送るための基盤です。
これらの学びは、一朝一夕に身につくものではありません。でも、今日から始めることで、確実に明日の自分は今日の自分より成長しています。
最後に、私の好きな言葉を贈ります。「The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.(木を植えるのに最適な時期は20年前だった。その次に最適な時期は今である)」
46歳の今が、新しい学びを始める最適なタイミングなのかもしれません。一緒に学び、一緒に成長していきましょう。未来の自分が、今日の決断に感謝する日が必ず来るはずです。
追記:読者の皆さんへ
この記事を読んでくださった皆さんは、きっと学ぶ意欲に満ちた方々だと思います。もし共感していただけた部分があれば、ぜひ今日から一つでも実践してみてください。そして、あなたの学びの体験も、家族や友人と共有してください。学びは、一人で行うより、みんなで行う方が楽しく、効果的です。
46歳からの人生、まだまだこれからです。一緒に素晴らしい未来を創っていきましょう。

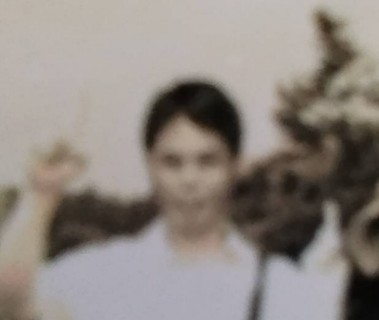








コメント