「世界で起きていることを、日本人はほとんど知らない」
このタイトルを見た瞬間、少しドキッとする人も多いんじゃないでしょうか。
谷本真由美さんの 『世界のニュースを日本人は何も知らない』 は、そんなショッキングな問いを投げかけてくる本です。
ニュースを見ているつもりでも、実は“都合よく切り取られた世界”しか見えていない――つまり日本人は「情報弱者」になりやすい。そんな現実を突きつけてきます。
この記事では、この本の内容を紹介しつつ、日本人がなぜ情報弱者になりやすいのか、そしてどうすれば抜け出せるのかを考えてみます。
日本人はなぜ「情報弱者」と言われるのか?
「情報弱者」というと、スマホやPCを使えない人のことを思い浮かべがちですが、本書で語られる“情報弱者”はもっと根本的です。
つまり「世界で大きく報じられていることを、日本人だけが知らない」という状況です。
例えば――
- 中国がアフリカでどんな影響力を広げているか
- ロンドンでは“白人イギリス人”がすでに少数派であること
- 日本が海外からどう評価されているか
こういった話題は、海外では普通にニュースで流れているのに、日本ではほとんど報道されません。
その結果、日本人だけが「世界の常識」から取り残され、知らず知らずのうちに情報弱者になっているのです。
本の概要
『世界のニュースを日本人は何も知らない』 は、世界と日本の「ニュースの落差」をテーマにした本。
章立てはこんな感じです。
- なぜ日本人は世界のニュースを知らないのか
- 世界の「政治」を日本人は知らない
- 世界の「常識」を日本人は知らない
- 世界の「社会状況」を日本人は知らない
- 世界の「最新情報」を日本人は知らない
- 世界の「教養」を日本人は知らない
- 世界の「国民性」を日本人は知らない
- 世界の重大ニュースを知る方法
どの章にも、「あ、日本のニュースではあまり聞かないな…」と感じる具体例がたくさん出てきます。
ページをめくるたびに「え、こんなに世界と日本で温度差があるのか」と驚かされる構成です。
著者・谷本真由美さんとは?
著者の谷本真由美さんは、国連の専門機関に勤務した経験を持つ人物。
いわゆる“外から世界を見てきた人”です。
そのキャリアを通じて、「日本の報道はあまりにも国内向けに偏っている」という違和感を持ち、本書の執筆につながりました。
国際的な現場を経験してきた人の言葉だからこそ、説得力があります。
本の中で印象的なトピック
1. 中国の影響力は、アフリカで拡大中
日本のニュースではほとんど触れられないけれど、中国はアフリカ諸国で積極的に投資やインフラ整備を行い、メディアまで買収している。
これにより、アフリカの報道は中国寄りになりやすいという現実があります。
2. ロンドンの人口構成
ロンドンでは、もはや“白人のイギリス人”は少数派。
これを「多様性」として前向きに捉える人もいれば、「伝統的な文化が失われつつある」と危機感を持つ人もいる。
こうした議論は海外メディアでは日常的に行われていますが、日本のニュースではほとんど聞かない話題です。
3. 日本の評価は意外に厳しい
日本人が「誠実でまじめ」と自己評価していても、海外では「日本は閉鎖的」「変化に弱い」といった声もある。
こうした外の視点を知らないままでは、国際社会での立ち位置を正しく理解できません。
日本人が情報弱者になる理由
ではなぜ、日本人は世界の情報に弱いのでしょうか?
本書では、いくつかの要因が語られています。
- 日本のメディア構造:視聴率・広告主の意向を優先し、海外ニュースを深掘りしない。
- 言語の壁:英語や多言語のニュースを直接読めない人が多い。
- 内向き志向:「海外のことは関係ない」と思いがち。
こうした背景から、日本人は「与えられた情報をそのまま受け取るだけ」の状態になりやすく、世界の流れを知らないまま取り残されてしまうのです。
この本を読むメリット
- 世界の出来事を“自分ごと”として考えられる
- ニュースをうのみにせず、「何が報じられていないのか」に気づける
- 海外との会話やビジネスシーンで教養として役立つ
- 40〜50代の“学び直し世代”に特におすすめ
読後にできるアクション
ただ読むだけで終わらせず、日常生活に活かすことも大切です。
- 海外メディアを直接のぞいてみる(BBC、CNN、Al Jazeera など)
- ニュースを「日本と海外でどう報じられているか」比べる
- 自分の意見をSNSや仲間内でシェアしてみる
こうした行動を習慣にすることで、少しずつ「情報弱者」から抜け出していけます。
まとめ
『世界のニュースを日本人は何も知らない』は、日本人がいかに“情報弱者”になりやすいかを痛感させられる本です。
けれど、同時に「今からでも視野を広げられる」という希望も与えてくれます。
ニュースをただ受け取るのではなく、背景にある構造を考えたり、海外の視点を取り入れたりすること。
それこそが、情報に振り回されずに生きる力につながります。
世界の出来事をもっと知りたい、情報の取り方をアップデートしたい――そう思うなら、この本は必読です。
 meibu
meibu情報は自分自身で取りに行くことも大切です!

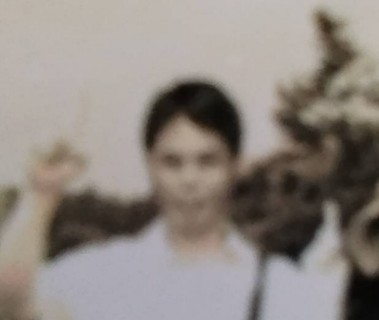

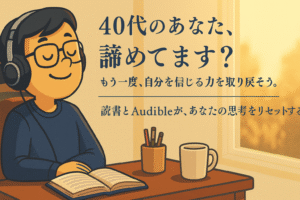

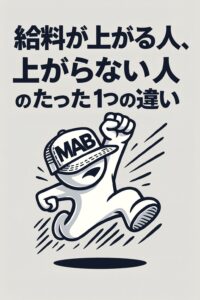



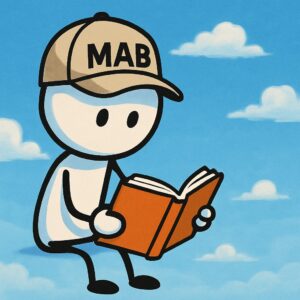
コメント