「新NISAってお得そうだけど、何から始めればいいの?」
「投資って難しそうで、損しないか心配…」
そんな風に感じていませんか?
2024年から始まった「新NISA(ニーサ)」は、投資で得た利益が非課税になる、とてもお得な制度です。
でも実際には、はじめの一歩で多くの人がつまずいてしまいます。
- どこで口座を作ればいいの?
- 何を買えばいいの?
- 始めたあと、どうすればいいの?
この記事では、40〜50代の初心者の方に向けて、
この「3つのつまずき」をやさしく解説します。
さらに、「自分で全部調べるのは大変…」という方のために、
無料でお金のプロに相談できるサービスも紹介します。
■ 新NISAとは?かんたんにおさらい
新NISAとは、投資で得た利益が非課税になる制度のことです。
普通の投資だと、利益の約20%が税金として引かれますが、NISA口座で運用すればその税金がゼロになります。
2024年からは制度が新しくなり、
- 年間の非課税枠が最大360万円
- 非課税期間が“無期限”に
- 「積立投資枠」と「成長投資枠」を両方使える
という、とても使いやすい制度になりました。
つまり、新NISAをうまく活用すれば、将来の資産づくりを効率的に進められるということです。
■ つまずき①:どの金融機関を選べばいいの?
NISAを始めるには、まず「どこで口座を作るか」を決める必要があります。
証券会社・銀行・ゆうちょ銀行など、選択肢がたくさんあるので、ここで迷ってしまう人がとても多いです。
金融機関ごとの特徴(初心者向け)
| 種類 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| ネット証券(SBI・楽天など) | 手数料が安く、商品が多い | 自分で操作が必要 |
| 銀行 | 窓口で相談できる | 手数料が高め |
| ゆうちょ銀行 | 全国どこでも対応。相談可能 | 商品数が限られる&運用コストやや高め |
「手数料が高い・安い」ってどういうこと?
投資信託を買うときや持っている間には、いくつかの**手数料(コスト)**がかかります。
これは「銀行の振込手数料」みたいなもので、サービスを使うための費用です。
初心者の方が特につまずきやすいので、実際の金額で見てみましょう👇
主な手数料の種類とタイミング
| 手数料の種類 | いつかかる? | 内容 | 目安金額(10万円の場合) |
|---|---|---|---|
| 購入手数料 | 買うとき | 投資信託を買う時の手数料 | 0〜3%(最大3,000円) |
| 信託報酬 | 保有中ずっと | 運用会社への管理費 | 年0.1〜1%(年間100〜1,000円) |
| 解約手数料 | 売るとき | 売却時にかかる費用 | 最近は0円が多い |
具体的なイメージで説明すると…
たとえば10万円で投資信託を買う場合、
- 購入手数料が3%だと、買った瞬間に3,000円が差し引かれ、実際に運用に回るのは97,000円。
- 購入手数料が0%(ノーロード)**なら、10万円すべてがそのまま運用に使えます。
そして、信託報酬(運用手数料)は毎日少しずつ差し引かれます。
たとえば年率0.5%なら、1日あたり約0.0013%ずつ、ファンドの中から自動的に引かれる仕組みです。
つまり、「気づかないうちにコツコツ引かれている」お金なんですね。
この数百円〜数千円の差が、10年・20年経つと数万円以上の違いになることもあります。
ゆうちょ銀行のNISA手数料をわかりやすく解説
ゆうちょ銀行でもNISA口座を開設できます。
ただし、手数料の仕組みは少し独特なので、ここで分かりやすく説明します。
ゆうちょの購入手数料
- ゆうちょ銀行では、多くの投資信託が「購入手数料無料(ノーロード)」です。
- 特に「ゆうちょダイレクト」や「ゆうちょ投信アプリ」で申し込むと、どの商品を買っても購入時手数料は0円です。
- 窓口購入も、初回は無料キャンペーンが行われています。
📖(参考:ゆうちょ銀行公式サイト[jp-bank.japanpost.jp])
🔹 ゆうちょの信託報酬(運用中コスト)
ゆうちょが扱うファンドの一部は、他のネット証券に比べて信託報酬が少し高めに設定されています。
たとえば、以下のような差があります👇
| 投資信託 | ゆうちょ扱いファンド例 | 信託報酬 | 同種の低コスト型(例) |
|---|---|---|---|
| TOPIX型 | つみたてんとうTOPIX | 約0.198% | eMAXIS Slim 約0.154% |
| 先進国株式型 | つみたてんとう先進国 | 約0.22% | Slim先進国株式 約0.102% |
| 新興国株式型 | つみたてんとう新興国 | 約0.374% | Slim新興国株式 約0.187% |
つまり、10万円を10年間運用すると…
- 信託報酬0.198%なら 約1,980円のコスト
- 信託報酬0.102%なら 約1,020円のコスト
となり、同じ運用でも約1,000円の差が出ることになります。
(出典:jp-bank.japanpost.jp、A-TEAM Money記事)
ゆうちょの解約手数料
ゆうちょ銀行では、売るときの手数料(解約手数料)は無料です。
そのため、「途中でやめても大きな損は出ない仕組み」になっています。
まとめると…
- ゆうちょは 購入時無料、保有中はやや高めのコスト
- ネット証券は 購入時も保有中も安め
- 「対面で相談したい人」にはゆうちょが安心、「手数料を抑えたい人」にはネット証券が有利
でも、「どれを選べば自分に合っているのか分からない…」
そんな方も多いはず。
そこでおすすめなのが、「ガーデン」という無料相談サービスです。
■ つまずき②:商品選びが難しい…「投資信託」って何?
投資信託とは、プロがあなたの代わりに運用してくれる“詰め合わせパック”のような商品です。
少額から世界中に投資できるので、初心者にピッタリです。
ただ、投資信託は数千種類あり、どれを選べばいいか分からない人がほとんど。
おすすめは次のような「インデックス型」の投資信託です👇
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 全世界株式型(オール・カントリーなど) | 世界全体に分散投資できる |
| 全米株式型(S&P500など) | アメリカ経済の成長に連動 |
| バランス型 | リスクを抑えて安定運用 |
信託報酬が低く、長期的に安定して成長する傾向があります。
ただし、「どのタイプが自分に合っているか」は、
家族構成や収入、老後の目標によっても変わります。
■ つまずき③:始めたあと、どう運用・見直しすればいいの?
新NISAは「長く続けること」が大切。
でも途中で「このままでいいのかな?」と不安になるのは自然なことです。
そんな時は、
- 積立額を無理のない金額に調整
- リスクを分散する(1つの国や商品に偏らない)
- 年1〜2回、運用の見直し
これでOKです。
でも、判断が難しいときは、お金の専門家に相談するのが一番安心です。
「ガーデン」なら、オンラインで気軽にFP(ファイナンシャルプランナー)に相談できます。
■ まとめ|迷ったら、“プロに相談してみる”という選択肢を
新NISAは、制度を知るだけでなく、
「どう活用するか」で将来の差が大きく変わります。
- 手数料をできるだけ抑える
- 自分に合った投資信託を選ぶ
- 継続して見直す
この3つができれば、初心者でも安心して資産を増やしていけます。
でも、最初からすべてを自分で調べるのは大変。
そんなときは、無料で相談できる「ガーデン」を活用してみてください。
✅ 無料でFPに相談できる
✅ 勧誘なしで安心
✅ 家計全体の見直しもできる

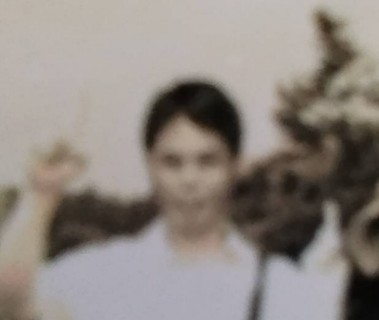








コメント