アフィリエイトブログは、うまく運営すれば副収入を得られる魅力的な方法です。でも、記事を書くときにはちょっとしたコツや注意点があります。特に初心者の方にとって、法律やルールと聞くと少し難しく感じるかもしれません。
この記事では、アフィリエイトブログを運営するうえでの「記事作成における注意点」を、一般的な観点から法律的な側面までを説明します。
 meibu
meibuこれからアフェリエイトを始めようとしている人や、アフェリエイトで副業を目指している人は予備知識として是非読んでくださいね!
読者の立場に立った記事を書く
まず一番大切なのは、「読者ファースト」の気持ちです。たとえば、あなたが「一人暮らしにおすすめの炊飯器」を調べているとしましょう。そのときに、「3合炊きの炊飯器ランキング」や「手入れがラクな炊飯器はこれ!」といった記事を見つけると、「今の自分にピッタリかも」と思って読みたくなりますよね?
逆に、ただ商品リンクだけを並べていたり、「この商品は最高です!」という感想しかない記事だと、すぐに閉じてしまうかもしれません。
読者は何か悩みや疑問を持って記事にたどり着きます。そのニーズに具体的に応える内容であること、そして「この人は自分と同じ目線で考えてくれている」と感じてもらえるような書き方が大切です。
【図解:読者の行動フロー】
検索(例:「一人暮らし 炊飯器 おすすめ」)
↓
あなたの記事にアクセス
↓
結論・内容を読む
↓
「自分に合いそう」と思えば購入・行動へ
この流れを意識することで、読者の「知りたい→行動したい」という気持ちに自然に寄り添った記事づくりができます。
具体的なポイント
- タイトルは「読者が検索しそうな言葉」で考える
- 結論を先に書き、理由や詳細をあとに続ける
- 難しい言葉は避けて、シンプルな表現を使う
- 実体験や使用感があると信頼性がアップ
アフィリエイトリンクは自然に配置する
商品やサービスの紹介をする際、無理に売り込むような文章は読者に警戒されがちです。あくまで「おすすめ」として、自然な流れでリンクを貼ることが大切です。
避けたい書き方
- 「今すぐ買うべき!」といった押し付け口調: 「このサプリを飲めば1週間で絶対痩せます!」というような表現は、押し付け感が強く、信頼を失いやすくなります。
- 一つの商品しか紹介せず、選択肢がない: モバイルバッテリーを紹介する際に「この商品しかない!」と1つだけを推すと、読者が比較検討できません。複数商品を並べて紹介する方が親切です。
- デメリットを一切書かない: 「軽くて大容量で完璧なモバイルバッテリー!」とだけ紹介するのではなく、「ただし少しサイズが大きめなのでポケットには入りにくいかも」といった欠点も伝えると信頼されます。
おすすめの書き方
- 複数の選択肢を提示し、比較する
- メリットだけでなくデメリットも伝える
- 実際に使った人の感想やレビューを引用する
たとえば、次のような表を使うと、読者は内容を一目で理解しやすくなります:
| 商品名 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| モバイルバッテリーA | 軽量・大容量・価格が手頃 | サイズが大きめでポケットに入らない |
| モバイルバッテリーB | コンパクトで持ち運びやすい | 容量がやや少ない・価格が高め |
このように、文章だけでなく視覚的な比較表を入れることで、読者にとって「自分に合った選択」がしやすくなります。また、読者に「選ばせる」ことができると信頼感も高まります。
画像や図解を活用して分かりやすく
文章だけだと読みにくい場合もあります。適度に画像や表、箇条書きを使って、視覚的にわかりやすくしましょう。
- スクリーンショットや図解は著作権に注意
- フリー素材を使う際も出典元を明記
- ALTタグを入れるとSEOにも有利
正確な情報を書く(ハルシネーション対策)
ここからは、ちょっとゆるっとしたセミナーっぽくいきましょう。
最近よく聞く「ハルシネーション」って言葉、ちょっとこわそうに聞こえますが、AIがそれっぽく“ウソをついちゃう”ことなんですね。たとえば、「存在しない本のタイトルを堂々と教えてくる」みたいな。
便利なAIですが、完璧じゃないんです。だからこそ、人間の目で確認するってめっちゃ大事。ここで、AIで作った情報と、人が地道に調べた情報の違いをサクッと見比べてみましょう:
| 情報の出所 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| AIツール(ChatGPTなど) | 幅広い知識を元にスピーディに文章生成ができる | 最新の情報や細かい数値に誤りがある可能性があるため、必ず事実確認が必要 |
| 人間によるリサーチ | 信頼できる情報源からの確認が可能 | 時間がかかるが、根拠のある情報を提供できる |
どうですか?この比較表を見ると、「AI任せっきりじゃダメだな〜」って実感わきますよね。
AIをうまく使えば時短にもなるし、アイデアも広がる。でも「書いた内容をチェックするのは自分の責任!」という気持ちを忘れずにいきましょう。ちょっと面倒でも、あとで信用を失うリスクを減らせますよ。
- 出典があるか確認する
- 公的機関や公式サイトの情報を引用する
- 数値や統計は必ず調査元を記載する
著作権・肖像権に配慮する(法律的な注意点①)
著作権とは?
他人が作った画像・文章・音楽などには著作権があります。無断で使用すると法律違反になります。
どうすればいい?
- 画像やイラストはフリー素材サイトを使う(例:いらすとや、O-DAN)
- 他サイトの文章をコピーしない(引用するなら明記)
- 自分で撮った写真や自作イラストを活用
ステルスマーケティング禁止(法律的な注意点②)
「広告であることを隠して紹介する行為」は2023年10月から違法となりました。
どう書けばOK?
- アフィリエイトリンクを貼る記事には「※本記事にはプロモーションが含まれています」と明記する
- 商品紹介部分の冒頭か末尾に書くのが一般的
- あくまで個人の意見や体験談として表現する



大丈夫!“この記事にはプロモーションを含みます”って一言書くだけでOKだよ。ちゃんと『広告ですよ』って伝えるのが大事なんだ!
薬機法や景表法に注意(法律的な注意点③)
薬機法とは?
薬機法(旧・薬事法)は、医薬品や健康食品、美容アイテムなどについて、「どんな効き目があるか」を表現する際のルールを定めた法律です。
たとえば、サプリメントの紹介記事で「このサプリを飲めば必ず花粉症が治る!」といった表現は、科学的な証拠がなければ違法になります。
また、「〇〇成分がガンを治す」と書くのも、薬機法違反になる可能性があります。健康食品や化粧品、ダイエット系の商品を紹介する場合は特に注意が必要です。
初心者向けのポイント
- 「○○に効く」と断言しない(→「○○に悩む方に人気」など言い換えましょう)
- 「個人の感想です」と書いても、誤解を招く表現はNG
- 曖昧でも過剰な期待を与える言い回しには注意(例:「奇跡のサプリ」「これで人生が変わった」など)
景表法とは?
「実際よりもずっとすごい」と読者に動かさせるような言い方はしちゃだめだよ。これは普通の社会常識にもとづいた「普及表示法」という法律で止められています。
たとえば、ただのシャンプーなのに「このクリーナーで病気が治った人群統計で、100%の人が元気をとり戻しました!」などと書いてしまったら、それは驚かしや誤解を与える表現とみなされて、法律違反になることもあります。
しっかり格評されるデータや、実際の情報などに基づいた表現にすることが大切です。
注意すべき表現
- 「絶対に治る」「100%効果あり」はNG
- 「個人の感想ですが…」と書いても、誤解を招くとアウト
- 根拠がないデータやランキングの掲載は控える
Googleのポリシーを意識する
検索エンジンからの評価は、アフィリエイトブログの生命線です。Googleが重要視している「E-E-A-T」の概念を理解し、それに沿った記事作りを意識しましょう。
E-E-A-Tとは?
以下のような4つの要素を指します:
| 要素 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 経験(Experience) | 実際に体験したことをもとに書かれているか | 商品を使ってみた体験談や写真など |
| 専門性(Expertise) | その分野に関する知識やスキルがあるか | 資格や業務経験に基づいたアドバイス |
| 権威性(Authoritativeness) | 情報提供者として信頼できるか | 業界での評価、他サイトでの引用実績など |
| 信頼性(Trustworthiness) | 正確で安全な情報かどうか | 情報源の明記、公的機関のデータ引用など |



E-E-A-Tを意識することは、SEOだけでなく、読者との信頼構築や収益化にも直結するというわけです。
信頼性を上げるには?
- プロフィールに「誰が書いたか」を明記する
- 実際の経験や資格があれば記載する
- 他の専門サイトや公的機関へのリンクを貼る
定期的な見直しと更新が大事
一度書いた記事も、時間がたつと情報が古くなります。定期的にチェックし、必要に応じて内容をアップデートしましょう。
- 商品リンク切れのチェック
- 情報の鮮度を保つ
- 読者のコメントやアクセスデータを参考に改善
最後に:読者と信頼関係を築く気持ちで
アフィリエイトは、単に「商品リンクを貼れば稼げる」というほど甘くはありません。多くの人が「副業で収入を得たい」「今より少しでも生活を楽にしたい」と思ってこの世界に足を踏み入れますが、実際には読者に信頼される記事を書かなければ成果にはつながらないのです。
たとえば、自分が友人に「この加湿器いいよ!」とおすすめする場面を想像してみてください。ただ「これ、安いから買ってみて」と言うよりも、「実際に使ってみて、喉が痛くなくなったし、静音だから寝るときも気にならないよ」と伝える方が、相手も「それ、いいかも!」と思ってくれるはずです。
読者も同じです。「この記事を書いた人は、自分の悩みをわかってくれている」「本当に使ってみておすすめしているんだ」と感じてもらえる記事こそが、信頼され、最終的に商品購入につながるのです。
一つひとつの記事が、誰かの役に立ち、「読んでよかった」と思ってもらえるような内容であれば、自然とあなたのブログにファンが付き、長く続けるうちに収益も生まれてくるはずです。

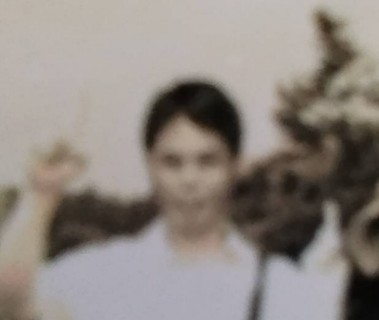
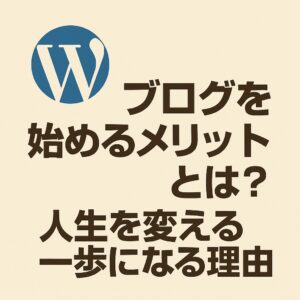
コメント